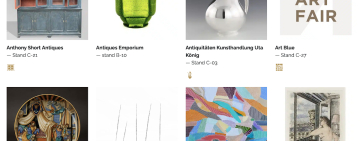その2 【雨だれ】
太陽と月は惹かれあう。
芯から熱を発生させて炎と光をまき散らす太陽。その光を受け止め、反射させることではじめて輝く月。
しかし、マヨルカにたどり着いたのは、太陽のように陽気な男とその陰にひっそりと佇む女ではなくて、逆のパターンのカップルだったようだ。
フレデリック・ショパンとジョルジュ・サンドは、なにもかもが普通の世界を逆さまにしたカップルだ。女性であるサンドが華やかなオーラを発する太陽で、男性であるショパンは静かな夜に光る月のよう。
結核にかかり肺病を病んでいたショパンの療養を目的として、そしてパリの社交界のゴシップから逃れるために、この不思議なカップルはマヨルカ島を訪れた。季節は秋から冬にかけて。いかに南の島とはいえども、期待していたほど天候はよいものではなく、ショパンは医者が必要なほど弱っていたようだ。
今なら飛行機で2、3時間も飛べばパリからマヨルカまですぐに到着する。当時はどうやって旅行したのか、まだ汽車も十分に通っていない時代だ。馬車だろうか。現代の車でパリからバルセロナまで1000キロを10時間。ならば1週間も馬車に揺られれば、なんとか地中海までたどり着くか。南仏かスペインの海岸から船に乗ったのは確実だろう。
ショパンとサンドは二人っきりではなかった。サンドの2人の子供と召使いの女性1人が一緒だったという。結核で衰弱した高名なピアニストと、黒尽くめの女流作家の一行は、田舎の島では強烈に衆目を集めることになった。1838年11月8日に到着したが、しばらくすると主要都市であるパルマには居られなくなった。教会に行かぬ。女だてらに本を書いている。ピアノの旦那は結核にかかっている。島民にとってショパンたちは疫病神以外の何者でもなかった。
追い立てられるように、ヴァルデモッサの古い修道院に宿を求めた。ショパンの書き記した手紙を読むと、最初の数日は天気もよくて人々は夏の装いをしていると喜んでいるが、修道院に移った頃はすっかり冬となり、悪天候に苦しんだ。
私も季節はずれの風邪を抱えつつマヨルカに飛んだ。2日目になると、いよいよ体調が崩れてきた。
ホテルはパルマ郊外にある静かな町で、昔の邸宅を改築したらしい広々とした場所だった。朝は見晴らしのいいテラスでフルーツやハム、チーズ、ヨーグルト、菓子パンなど気のきいた食事をゆったりととることができる。お腹の大きい女性がフロントと食事スペースを優雅に取り仕切っていて、もう一人が裏方で食事の用意をしていた。
どうも私の体は自然治癒にまかせていても回復しない様子なので、宿のセニョーラに近くでいい病院がないか紹介してもらおうと思った。彼女に風邪の症状を見てくれる病院がないか聞いてみる。
エレガントな物腰で英語も堪能な才女であるセニョーラだが、やはり自身が身重の状態で病人と接するのは、生理的に嫌なのが伝わってくる。申しわけない。
「病院なら、この近くにありますよ」
「今日は開いているかな?」
「ええ、大丈夫なはずです。調べてみますから、お食事しながらお待ち下さい」
「ときに、そこは英語が通じますか?私はスペイン語がまったくできない」
「まあ、大丈夫でしょう。なんとかするでしょう・・・」と言いながら、大抵のことは、なんとかこなしてしまうラテンのおおらかさが、そこにあった。
食後に、はたして宿から徒歩2分のところにある村の診療所といった病院に出向いた。やはり英語はあまり通じなかったが、なんとか処方箋を書いてもらい、薬局でもスペイン語のみで切り抜けた。その気になれば、フランス語が非常に訛っているという覚悟で聞いていれば、ある程度の理解はできるのである。
さて。寝込むほどではないので、マヨルカ島の旅は続く。車を駆って一路北へ向かう。ショパンが逗留した修道院は、ヴァルデモッサという村にある。車なら30分で到着する。事前に完璧に調査していたわけではないので知らなかったが、意外に観光地として発達した場所になっている。土産物屋やレストランがたくさんある。駐車場に車を停めるのも一苦労だ。
広場の一角に「フレデリック・ショパンとジョルジュ・サンドの博物館」というのがあった。ここはショパン御一行様が滞在した修道院のこじんまりとした部屋が展示室として公開されている。
天井の高い修道院の長い廊下を通り抜けて行くと、ショパンの部屋がある。私が訪問した8月でも石の建造物はひんやりと冷たい。冬の寒い時期はさぞかし冷え冷えとした場所であったに違いない。ここにプレイエル社製のピアノをパリから運ばせ、ショパンは素晴らしい作品の数々を作曲することになる。
都会の喧騒から離れ、文化的な交流からは隔絶された場所で、ピアノの詩聖は自分の魂と向き合うことができたのか。なぜ、ここで、マヨルカの田舎の僧院で、創作の炎を立ち上らせることができたのか。不思議である。
寒々とした回廊には、フレデリック・ショパンが1838年12月20日から翌年の2月13日まで滞在したと石板に刻まれている。南欧だろうが、北半球が一番寒く、人間が孤独を感じやすい時期だ。
ピアノは容易にパリから飛んできたわけでもなく、主人であるショパンと一緒に船に乗ったわけではない。なにしろ往路ではスペインの税関で足止めをくらい、すったもんだの結果なんとか僧院に持ち込めた。帰りもいろいろ問題があり、結局、島に残していくはめになる。
博物館に島民の手記の翻訳が展示されているので、興味深く読んだ。
「ジョルジュ・サンドは美しい婦人で、輝く黒い瞳が印象的な知性にあふれた顔つきをしている。神々しいまでの髪が額を縁取り、頭の後ろでくくった髪には銀の美しい短剣が刺さっていた。いつも黒か濃い色の洋服に身を包み、大きな宝石がついた十字をヴェルヴェットの紐で首からさげ、腕輪には想い出の品よろしく指輪が多くぶら下がっていた」
「息子のマウリシオは、年の頃13か14か、か細く繊細で、言葉を発せず、小さなアルバムに興味をひいたものを熱心に描き込むのが好きだ」
「小さなソロンジュは女史の娘で、兄とは対照的に、生気溢れる闊達なブロンド娘である。盛んに動いては音を立て、シャツとズボンをフェルト帽の下にまとった姿からは、母親から受け継いだ長く美しい髪が腰のあたりまで伸びているのでなければ、行儀の悪い男の子と思われてもしかたのない様子だった」
「彼らに同行している音楽家のショパンは、その作品でよく知られた人で、とても具合が悪そうだった。健康を回復するために南国の気候を求めてきたのだ。数週間ここで滞在した後、ショパンが胸に由々しき問題を抱えていると知られ、パルマの人間は肺病患者の住んだ家には近づきもしないというほど恐れを持っているので、ここに至って宿の主はサンドに即刻立ち退くようにと告げたのである。友人の介入があって、ヴァルデモッサに小さな部屋を見つけることができて、彼女は嬉しそうだった」
というわけで、フランスからの旅人たちは、北部にある僧院に逃げ込むわけだ。
さすがタフな女性のサンドは『マヨルカの冬』という本を書いたりして、転んでもただでは起きない。島の風景を称賛しつつ、島民については辛辣な筆をふるった。
この手記を書いた婦人は、ショパンとサンドに対して親切に接したらしく、プレイエルのピアノを譲り受けることになる。いかに作曲家の大先生とはいえ、結核患者の弾いていたピアノを受け取る勇気を持った人間はマヨルカに数多くいるわけではなかったのである。
現代の我々からすれば、「ショパンの弾いたプレイエルのピアノ」しかもわざわざパリから取り寄せた楽器が、どれだけの歴史的な価値を有するかは重々理解できる。ショパンのピアノをお目当てに押し寄せる観光客の数も相当だろう。
その肝心のピアノはというと、、、どこにでもありそうなアップライト。よく見ると、竪琴と羽根ペンがあしらわれた金属プレートがつけられている。1838 - 1839という年号も見える。
小さなショパン博物館となった僧院の部屋には、ショパンの左手の石膏があった。
39歳で亡くなった天才ピアニスト。
ここにあるのはコピーだが、ショパンは死に際してデスマスクとデスハンドというのか左手の型を取られている。彫刻家オーギュスト・クレサンジェが制作した。サンドの娘ソランジュの夫である。右手は存在しないので、左手だけがかたどられたようだ。寡聞にしてショパンが左利きだったとは知らない。なぜ左なのか。
ショパンとサンドの二人は別れてしまったが、ショパンはソランジュに看取られて黄泉の国へと旅立った。血のつながらない娘が死の間際に側にいたことを見ても、太陽と月の決して切れない関係が続いていたのだと分かる。
ヴァルデモッサの修道院でショパンが作曲した「雨だれ」は、悪天候のマヨルカでショパンが生み出した静溢な音楽である。後半にあふれんばかりの情感がほとばしる峠を越えると、あとは諦念に身を貫かれたように、ただただ美しく音楽が響き渡る。